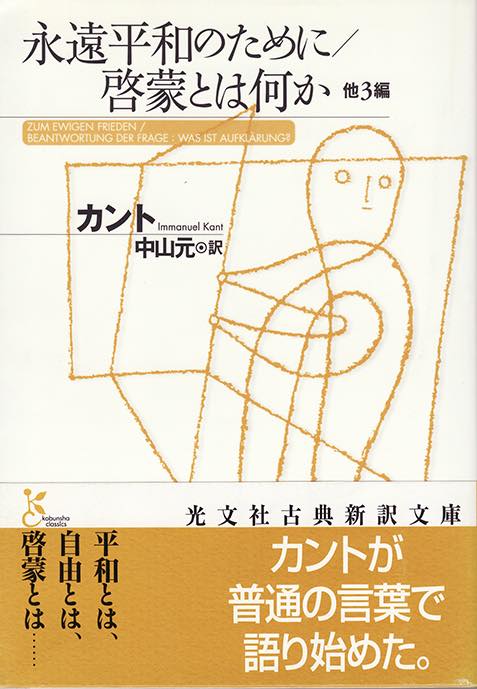
“「自分の理性を使う勇気をもて」”——— p.10
題名を見て食傷めいたものを感じた。平和という言葉は、歴史の中で弄ばれ続けた結果、手垢にまみれ、陳腐な響きすら帯びてしまった。しかし、本書の中で使用されるこの言葉は、潔白で、危険に満ちて、瑞々しい。それは、お仕着せの決まり文句としてではなく、人類の肯定を目的に、カント自身が考え、紡ぎだした言葉だからだろう。彼は本書で、自ら思考することを説き、実践している。孤独な思考を通して、議論し合うための自分の言葉を産み出そう。
黙字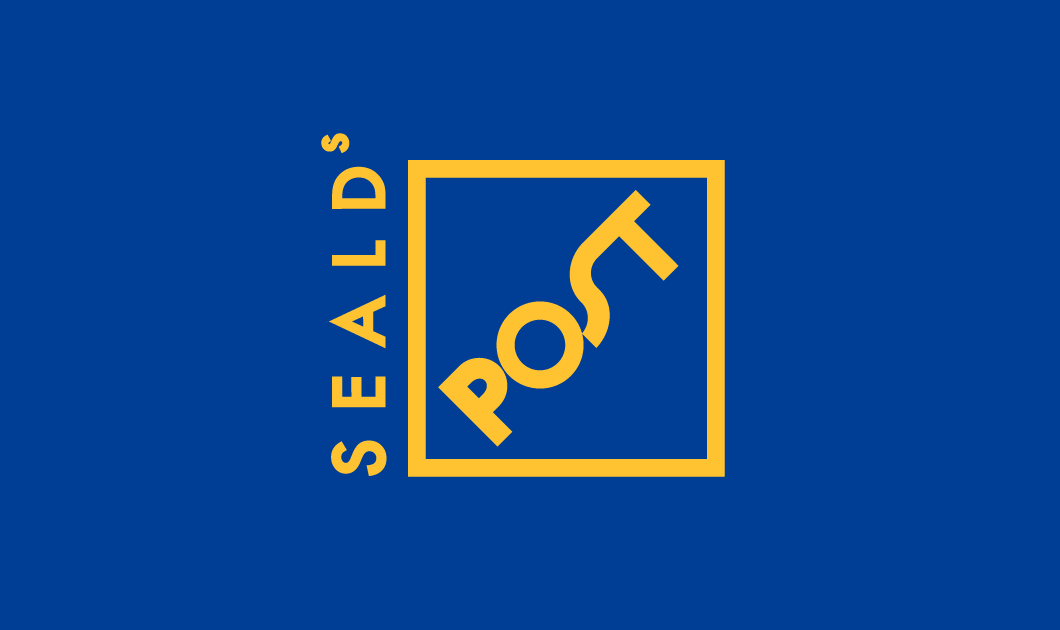
光文社古典新訳文庫 2006年
カント 著; 中山元 訳
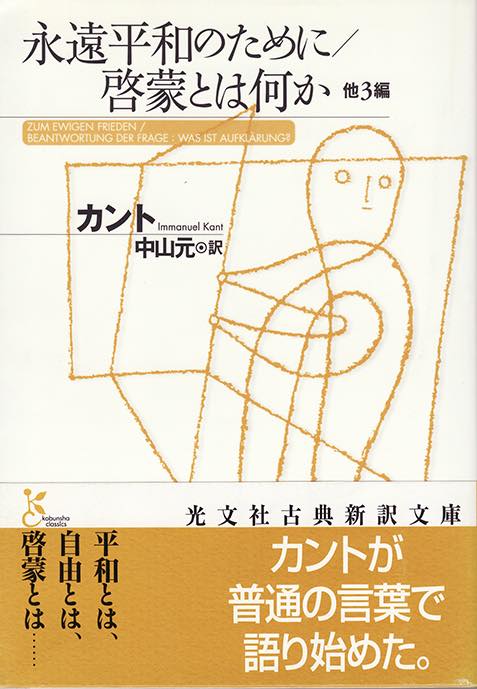
“「自分の理性を使う勇気をもて」”——— p.10
題名を見て食傷めいたものを感じた。平和という言葉は、歴史の中で弄ばれ続けた結果、手垢にまみれ、陳腐な響きすら帯びてしまった。しかし、本書の中で使用されるこの言葉は、潔白で、危険に満ちて、瑞々しい。それは、お仕着せの決まり文句としてではなく、人類の肯定を目的に、カント自身が考え、紡ぎだした言葉だからだろう。彼は本書で、自ら思考することを説き、実践している。孤独な思考を通して、議論し合うための自分の言葉を産み出そう。
黙字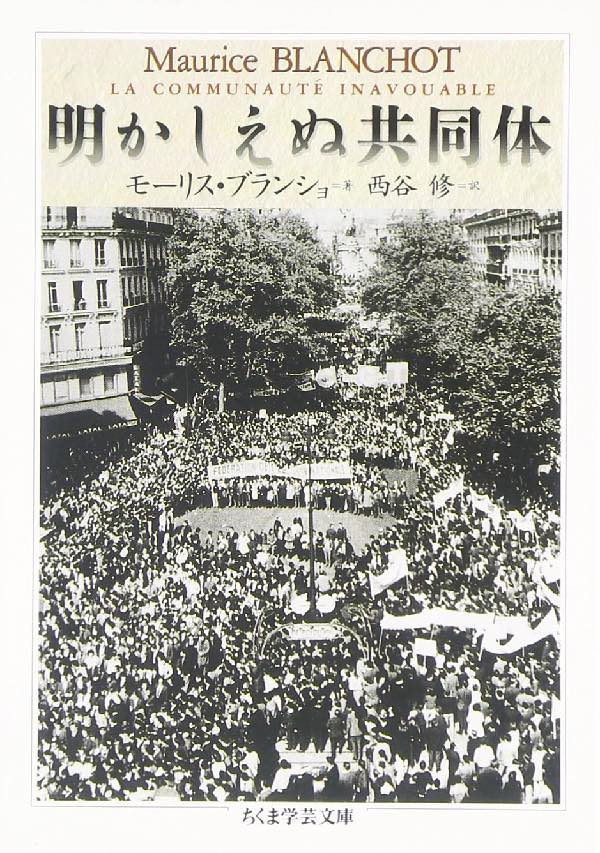
“共同体は至高性の場ではない。それはおのれを露呈しながら他を露呈させるものである。共同体は、それを締め出す存在の外部を内に含んでいる。”
生きるということ、死ぬということ。 とても個人的なことに思える。 私の生を、私の死を、誰も代わってはくれない。 しかし果たして、私は独り死ぬことができるだろうか。 「私は死んだ」と言える人間はどこにもいないはずだ。 私はせいぜい他者の死に立ち会うことしかできない。「私が考えることは自分独りで考えたものではない。」こう言ったバタイユのことを考え続けたブランショ。 そのブランショを考え続ける私とは。 まさにここに共同体は出来する。
羽鳥涼