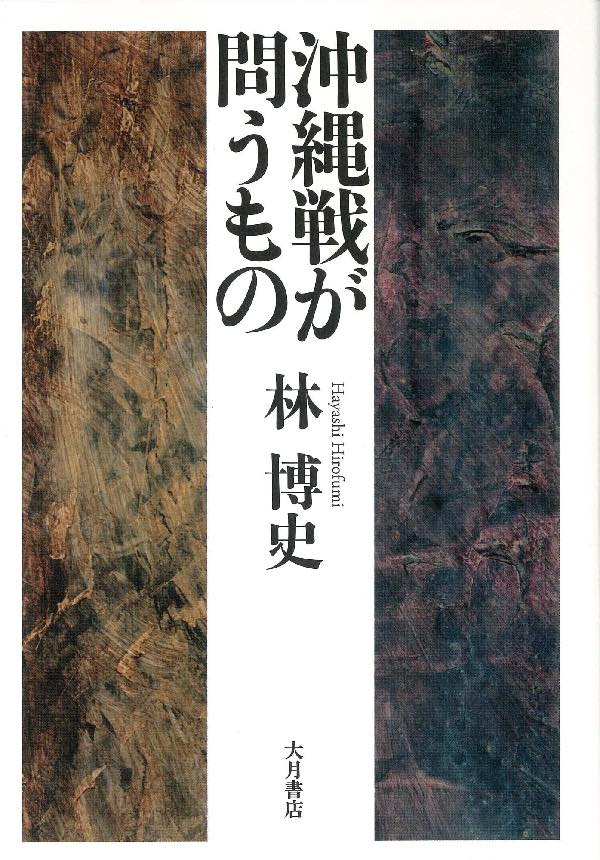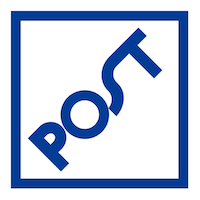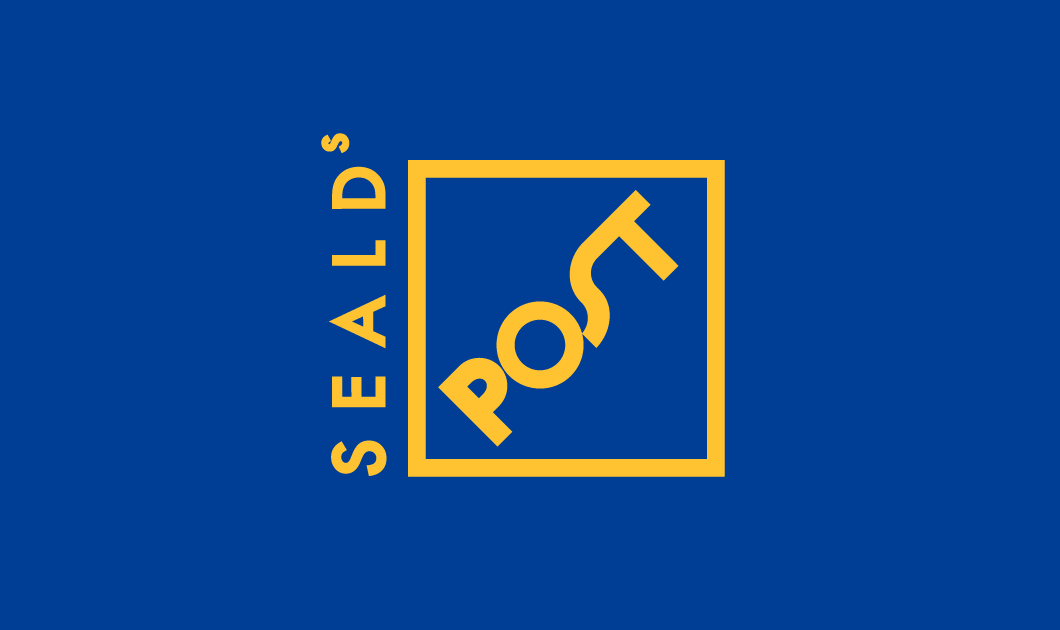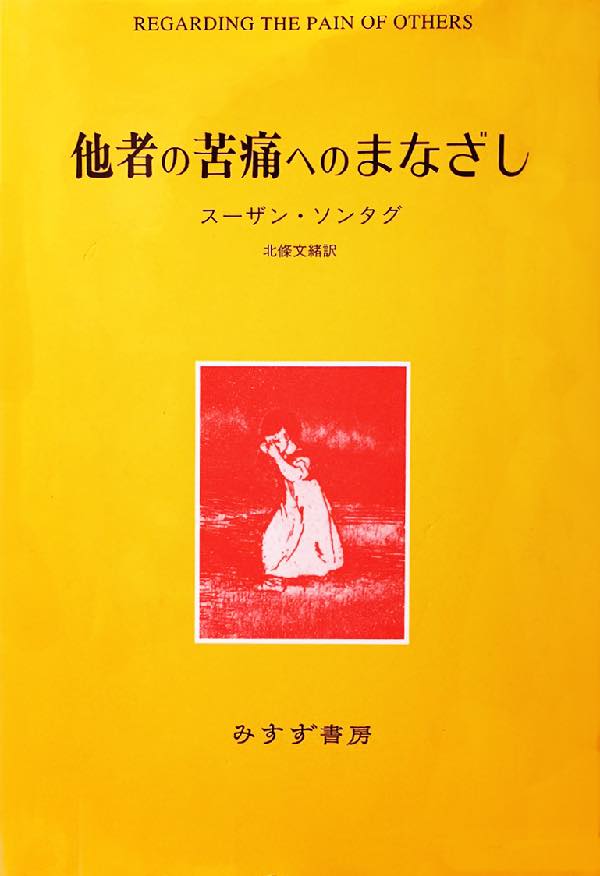“戦争責任をとるということは、言葉で謝るだけではなく、同じ過ちをくりかえさないように政治社会を作りなおすことではないだろうか。”——— p.159
戦争の経過。死者数の羅列。戦場の名前。それだけでは重要なことが切り落とされるだろう。そこには、違う背景を持った他の誰でもない一人一人が存在したという事。その戦争でそういった「個人」の命や尊厳が奪われた事。唯一の地上戦が行われた沖縄戦。そこから学ぶべきは、軍や政府という 「組織」が進めた戦争に、どのような「個人」が巻き込まれていったのかということだろう。それに対する想像力が同じ過ちをくりかえさないための社会を作る。
いたる
BOOK'S SELECTION
他者の苦痛へのまなざし
スーザン・ソンタグ 著; 北條文緒 訳
みすず書房
2003年
“あなたたちには理解できない。あなたたちには想像できない。” ——— p.127
日々膨大に流れる言語や写真、映像の情報を介して得る「他者の苦痛」。それらを目の当たりにし、反戦と平和、貧困や格差の是正、差別の撤廃を叫ぶ人々。そして目や耳を塞ぎ、傍観し、無用な批判や罵声を発する人々。けして誰も本当にはその苦痛をわかりはしない。本書は訴え、呼びかけ、問うている。私たちの失いかけた感受性を、想像力を、注意力を再び取り戻し、現状に抗い続ける意志を絶やしてはならない。いま、スーザン・ソンタグのいうラディカルの意味を自らに問い直したい。
ゆいぽよ
POST(ポスト)は、様々なかたちで日本の政治や選挙について考えるきっかけを提供するウェブサイトです。