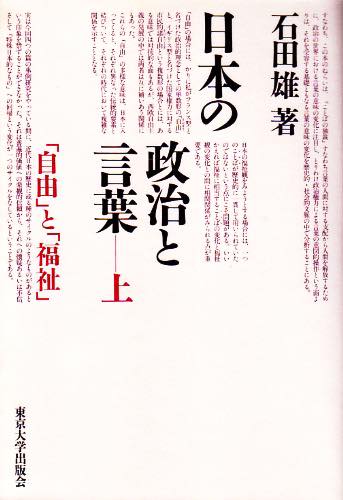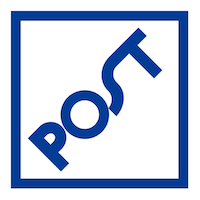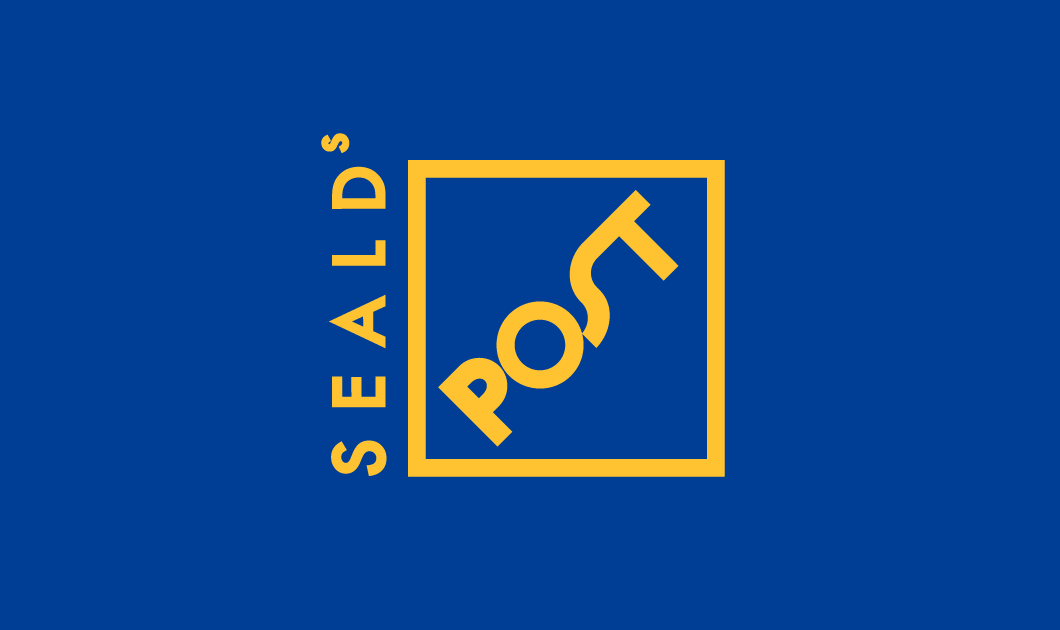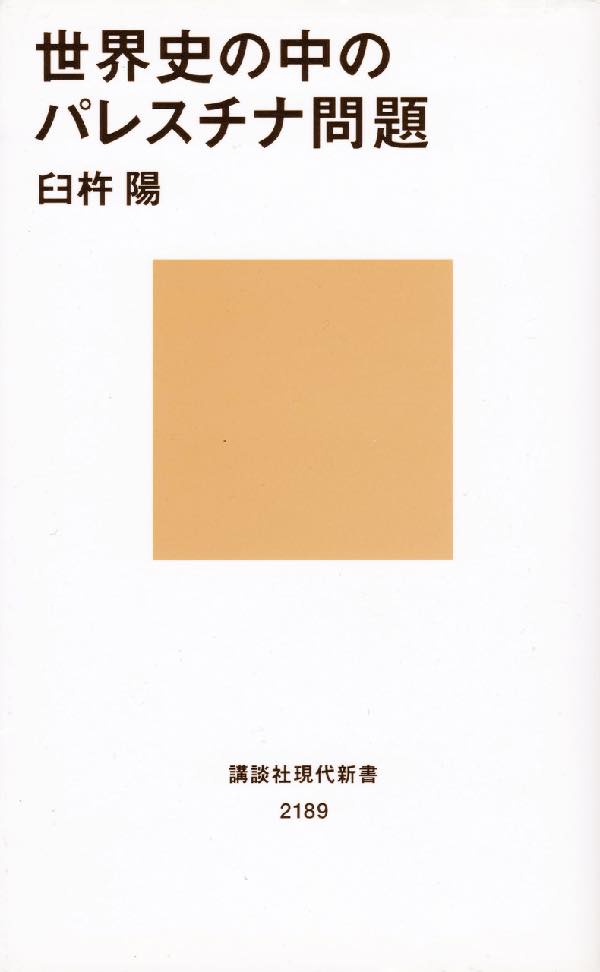“一つの言葉が、いろいろな意味を持ちうる中で、 なぜある場合に一つの意味が支配的であるかを、その社会的・歴史的文脈の中で明らかにすることが必要なのである。”——— p.6
あなたにとっての「自由」の言葉の主体は「リベルテ(個人)」ですか、それとも「リバティー(権力に対する市民)」ですか。“ことば”が独立した道具ではなく、「いつ・だれが・ どこで・なぜ」用いるかによって変化するものであることは、 分かっていても意識しづらい。「自由」や「福祉」など普遍的な価値を持つ言葉が、日本の政治史の中でどう変化してきたのか。この視点をもつことは同時に、それぞれの時代にとっての「価値」を再認識することでもあるのだ。
みつ
BOOK'S SELECTION
世界史の中のパレスチナ問題
臼杵陽 著
講談社現代新書
2013年
“イスラエル人であれ、パレスチナ人であれ、それぞれの立場から「平和」を求めているはずです。” ——— p.4
現代において最も深刻な民族紛争のひとつである、パレスチナ・イスラエル問題。 これは単なる宗教対立ではない。 世界が経験してきた歴史の縮図であり、近代国民国家が生み出した問題でもあり、 また、差別とは何かを私たちに問いかけるものでもある。 パレスチナ・イスラエルが語る歴史はあまりにも重く、 複雑で、今なお解決の糸口は見えてこない。 しかしだからこそ、このことを踏まえた上で、 現実を変えるために私たちは繰り返し考えていきたいのだ。
もえこ
POST(ポスト)は、様々なかたちで日本の政治や選挙について考えるきっかけを提供するウェブサイトです。