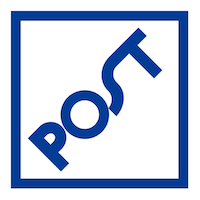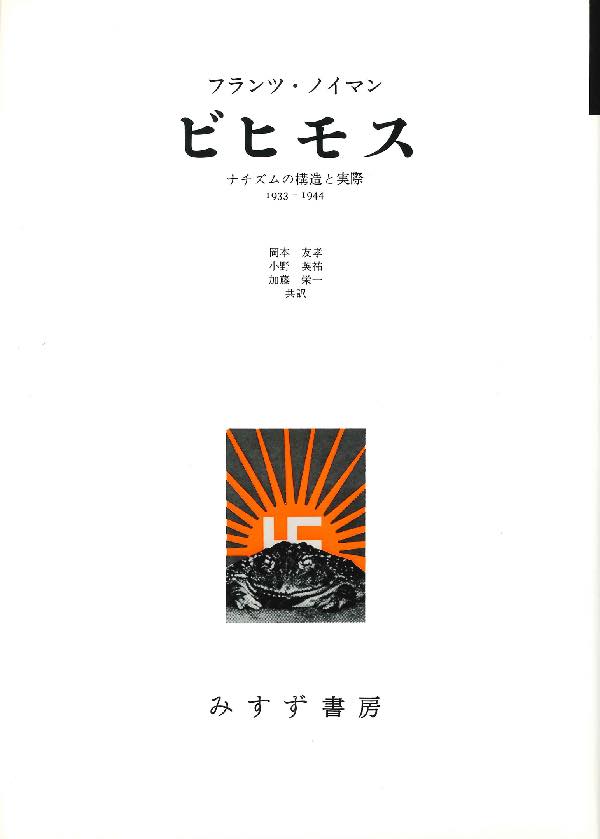少し湿った黄土色の紙のランチボックスの中身は妙に生々しい色をしたウインナーが三本と汗をかいた黄緑色のスクランブルエッグに、それとは対照的にすっかり乾ききった丸いパンがふたつ。仕方なくパンを半分にちぎってプラスチックカップに残っていた水で流し込む。あと三時間。短い針があと三回まわったら、私はまた一から言葉の発し方や目の動かし方やなんかを自分に教えてやらなきゃならない。
新宿行きの電車にゆられる土曜の午後八時過ぎ。ふと身に覚えのある臭いが鼻をつく。二つ隣りに座る女が爪を塗っていた。彼女が揺れる電車の中でこれはなかなか器用に緑の液のついた小さな筆を滑らせるのを周りに座った人間が見ていた。斜め前の女は眉をひそめ、革靴の男は咳払いをした。誰も一言も発さなかった。電車は新宿に着く。皆黙って降りて行った。私も染みのついたケルアックを真っ白なシャネルに突っ込んで、黙って降りる。ひょいと跨いで歩くのもぶつからないようにと足早に遠ざかるのも、どっちにしたって結局は同じことだ。
渋谷の街を歩く。路地を一本裏に入れば吐瀉物と精液の混じる臭いが立ち込めるあの街を、歩く。あたり一帯に流れる空気が時折喉を狭めるのは決して排気ガスのせいだけじゃない。ファッションビルに吸い込まれていく女のハイヒールの踵が汚れていた。ヘイ、ビューティフルって声をかけては邪険に追い払われる黒人の首にぶら下がる金の大きなチェーン。
明日も彼は路上に立ってセンター街を通り過ぎてゆくその誰かへ声をかけ続けるに違いない。私はまた歩く。煤けたコンバースの紐はしっかりと結ばれている。向かい風はまっすぐに伸ばした髪を散らかしたけれど、もう頬に突き刺さるような冷たさなんてとっくのとうに消え去っていた。